 古地図
古地図
江戸の古地図|江戸幕府が隅田川に橋をかけなかった理由|橋がないことで起きた悲劇
 古地図
古地図 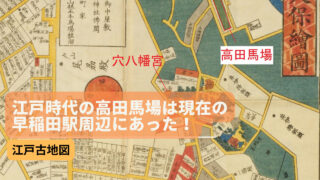 古地図
古地図 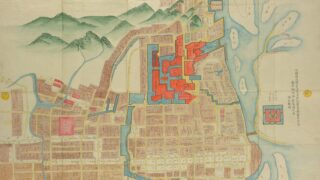 古地図
古地図 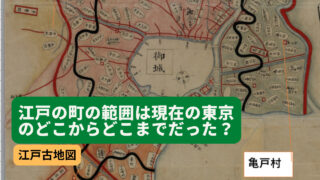 古地図
古地図 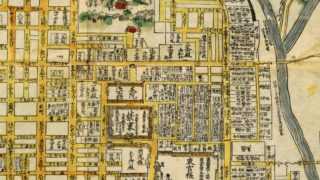 古地図
古地図  日本史
日本史 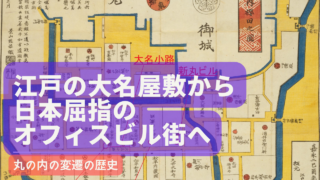 古地図
古地図 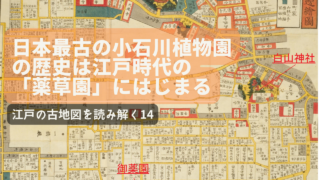 古地図
古地図  ギリシア神話
ギリシア神話  世界史
世界史  お寺
お寺 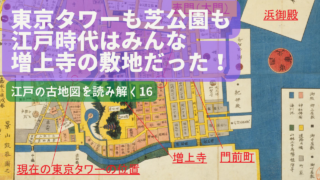 古地図
古地図 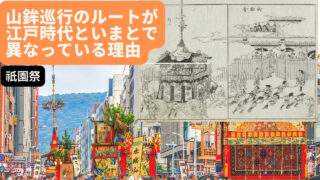 神事
神事  神事
神事 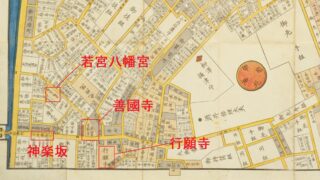 古地図
古地図  神事
神事  神社
神社  古地図
古地図 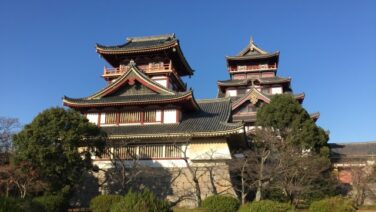 日本史
日本史  日本史
日本史  日本史
日本史  日本史
日本史 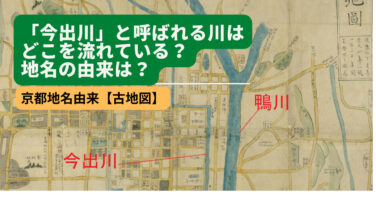 古地図
古地図 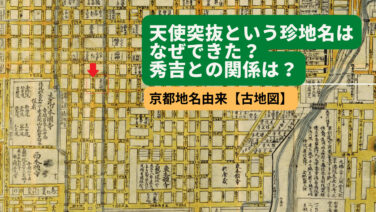 古地図
古地図 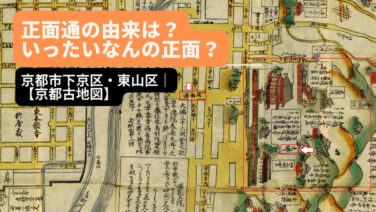 古地図
古地図 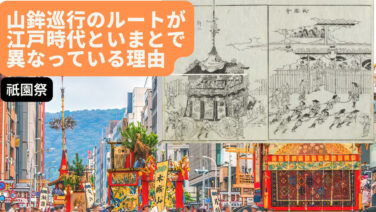 神事
神事 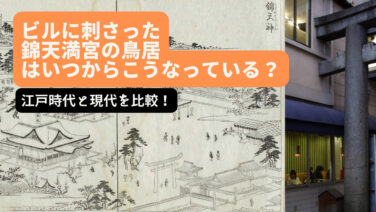 江戸時代
江戸時代