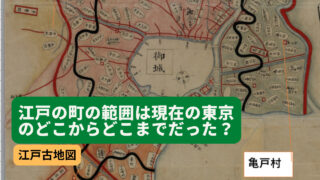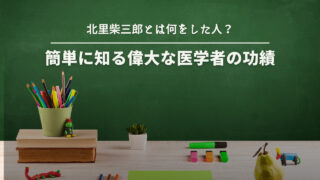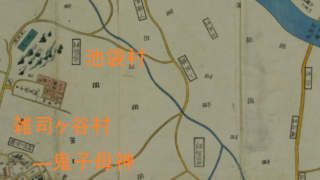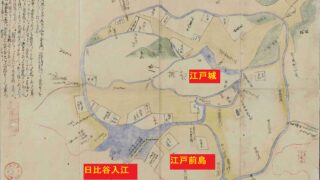吉良、討ち取ったり
時は元禄15年(1702)12月14日深夜、元赤穂藩の浪士たちは主君・浅野内匠頭長矩の仇である高家・吉良上野介義央の屋敷に討ち入り、見事討ち取った。世に知られる「赤穂浪士討ち入り事件」である。
彼らは吉良邸に討ち入ったあと、浅野家の菩提寺・泉岳寺へ向かい、主君の墓前に吉良の首を供えて弔った。
はたして彼らは吉良邸から泉岳寺までどのようなルートをたどったのか。まずは吉良邸があったJR両国駅周辺へ向かう。
吉良邸跡
吉良邸跡は現在、本所松坂町公園として整備されている。JR両国駅の東口を出て、南へ徒歩7分ほどのところに位置する。

じつは、もともと吉良邸は江戸城に近い呉服橋周辺にあった。しかし元禄14年(1701)9月、江戸外れの地である本所へと移されている。江戸城松之廊下で浅野内匠頭が吉良上野介を斬りつけ、切腹を命じられた刃傷事件から6か月後のことである。
その背景には、赤穂浪士らの吉良邸への襲撃を憂慮した周辺の大名家からの苦情があったと考えられている。
公園の面積は、往時の吉良邸の80分の1ほどでしかない。しかし園内には、吉良方の死者を祀った慰霊碑が残るなど、わずかながらに当時の事件を記憶をいまに伝えている。なお、公園の周囲に巡らされた石壁は、高家の格式を示す海鼠壁長屋門を模したものとなっている。
回向院
元禄15年12月15日午前6時、吉良の首を取った赤穂浪士は吉良邸裏門から引き揚げ、隣接する回向院にひと時の休息を求めた。
回向院は明暦3年(1657)の創建である。江戸市中のじつに3分の1を焼き尽くした明暦の大火で亡くなった人々を祀るために建立された浄土宗の寺院だ。

だが回向院は、返り血に濡れた赤穂浪士の境内への立ち入りを拒絶した。そこで赤穂浪士たちはやむなく、そのまま浅野内匠頭が眠る泉岳寺へ向けて出発した。
永代橋
赤穂浪士らは陸路で泉岳寺へと向かったが、途中で隅田川を渡る必要があった。回向院近くには両国橋が架かっていたが、彼らはそこを渡らず、隅田川の東岸を南へ下り、永代橋を渡った。当時の永代橋は現在よりも150メートルほど上流にかかっていた。
彼らが両国橋を避けたのは、毎月15日が江戸城の登城日にあたっており、両国橋が大名や旗本の登城路となっていたためであった。
永代橋を渡る前に、赤穂浪士たちはひとときの休息を取っており、かつてその地にあった味噌店の乳熊屋の主人が彼らに甘酒を振る舞ったという。現在、乳熊ビルの前に「赤穂浪士休息の地」の碑が残る。

旧赤穂藩上屋敷跡
その後、彼らは隅田川西岸を南下。鉄砲洲(現・東京都中央区湊、明石町あたり)にあった旧赤穂藩上屋敷跡へ向かう。
江戸初期、赤穂藩の上屋敷は外桜田に置かれたが、明暦3年(1657)に鉄砲洲に移された。刃傷事件後は幕府に接収されて小浜藩上屋敷となっていたが、思い出深いこの地を避けて通ることはできなかったのであろう。
現在、中央区立明石小学校と聖路加看護大学がある一帯が赤穂藩上屋敷があった場所で、聖路加看護大学敷地の一角に「浅野内匠頭邸跡」の石碑が立つ。

泉岳寺
旧赤穂藩上屋敷跡に立ち寄ったのち、赤穂浪士らは現在の第一京浜が走る道を通り、目的地である泉岳寺へ到着した。本所の吉良邸からおよそ3時間という行程だった。
当時、赤穂浪士たちは吉良邸への討ち入りを「仇討ち」と称したが、浅野内匠頭の切腹は幕府が命じたことであり、彼らの行動は違法行為にあたった。
だが、人々はそんな彼らの義挙を賞賛した。彼らが泉岳寺に到着したとき、山門には多くの群衆が詰めかけ、彼らをあたたかい声で迎えたと伝わる。
境内に入った彼らは、まず井戸の水で吉良の首を洗った。このときの井戸が、現在も境内に残る。そして主君の墓前に首級を供え、彼らの大願は成就したのであった。
元禄16年(1703)2月4日、赤穂浪士たちは切腹に処され、この世を去った。その亡骸は、主君と同じ泉岳寺へと葬られた。
江戸時代の暮らしをさらに詳しく知りたい方におすすめの書籍
『一日江戸人』杉浦日向子(新潮文庫)
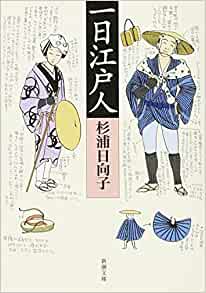
現代の江戸人・杉浦日向子による、実用的かつ、まことに奥の深い江戸案内書。
江戸美人の基準、三大モテ男の職業、衣食住など、江戸の人々の暮らしや趣味趣向がこれ一冊でわかる。試しに「一日江戸人」になってみようというヒナコ流江戸指南。
『現代語訳 江戸府内絵本風俗往来』菊池貴一郎(角川ソフィア文庫)
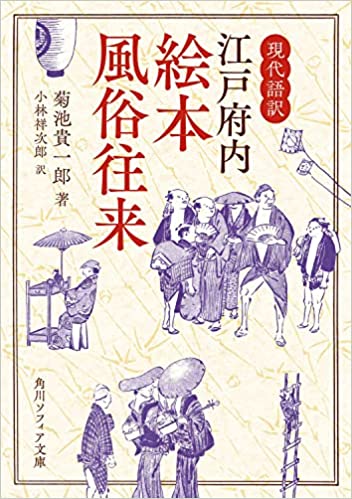
四季の行事から、日常の風景まで。江戸の風情を283点の絵と文で愉しむ。江戸の町の季節の移ろいや、武家・町人の行事・習俗・遊びのさまざまを、イラストとともに回顧する。江戸を知るための基本書、初の現代語訳。図版283点のすべてを収録。
『浮世絵でわかる! 江戸っ子の二十四時間 』山本博文監修(青春出版社)

棒手振・朝湯・寺子屋・蕎麦・天ぷら・初鰹・富くじ・相撲・手習い・水茶屋・駕籠屋・火消し・祭り・吉原・百物語…浮世絵で見るからもっと面白い! 江戸の暮らしの朝から晩まで。近年、発見され話題となった歌麿の肉筆画「雪月花」のひとつ『深川の雪』を収載。オールカラー128P。