対秦のため、再び諸国は合従軍を組織
前247年の河外の戦いののち、秦では荘襄王が亡くなり、13歳だった政が秦王として即位しました。のちの始皇帝です。しかしまだ幼かったため、その政務は宰相である呂不韋が取り仕切りました。
前243年に魏を支えた信陵君、そして安釐王が亡くなると、秦はこの混乱の隙を見逃さず、すかさず攻勢に出ます。前242年、蒙驁をして魏へ侵攻させると、山陽や雍丘など20もの城をおとし、そこに東郡を設置しました。こうして秦は、斉と国境を接することになりました。
この頃になると、中華世界は秦を中心として動いていました。諸国は単独では抵抗できない状態に陥っていたのです。
そのような状況下にあって、再び合従の機運が起こります。そして前241年、韓・魏・趙・燕・楚の5か国合従軍が成立しました。
盟主は楚。合従軍を率いる将には、楚の春申君が選ばれました。
春申君はもともと遊説家でしたが、その才能が楚の頃襄王に認められて楚に仕えるようになった人物です。そして頃襄王の子・考烈王の時代に令尹(宰相)に任ぜられました。
春申君率いる合従軍が函谷関に攻め寄せる
合従軍はまずかつて趙の地であった寿陵を秦から奪還すると、函谷関へと向かいました。秦にとって函谷関は東方からの侵攻を防ぐ重要な役割を果たしていた関所であり、合従軍にとってはどうしても落とさざるを得ない要衝だったためです。
一方、合従軍は本軍とは別に、別働隊を南から差し向けて秦の国都・咸陽へと迫ろうとしていました。主将は趙将・龐煖。趙・楚・魏・燕の4か国軍を率いた龐煖は合従軍の函谷関攻めと連動するように、秦の蕞へ攻め寄せました。
こうして秦は絶体絶命の危機に陥ることとなりましたが、死力を尽くして函谷関で迎撃にあたる秦軍の抵抗の前に、合従軍は苦戦。時間が経るにつれて秦軍に押されるようになり、結局は敗走を余儀なくされてしまいました。また、蕞を攻めていた別働隊もこれを落とすことができず、そのまま引き揚げています。
こうして函谷関の戦いは合従軍の敗北に終わり、以降、合従軍が結成されることはありませんでした。
なお、龐煖は兵を引き揚げたその足で秦と同盟関係にあった斉へと侵攻し、饒安を奪っています。
戦後、合従軍の敗北の責任はすべて春申君にあるとされました。春申君は考烈王の信任を失い、徐々に疎んじられていきます。その最期も哀れなものでした。
春申君は趙の食客・李園という男の妹を愛妾としていました。やがてその愛妾が春申君の子を身籠ると、彼女からこう唆されました。「私を王に献じ、私が男子をなせば、あなたの子が王となり、楚はあなたのものになります」と。これは当時、考烈王に子がなかったことにつけ込んで出世をしようとした李園の入れ知恵でした。
この頃、すっかり耄碌していた春申君は欲に溺れてこの策に乗ってしまいます。李園の妹は無事男子を産み、李園は王后の兄として着実に出世を遂げていきました。しかし、春申君に陽の目があたることはありませんでした。
前237年、考烈王が病で没すると、春申君の子は王として即位しました(幽王)。ですが春申君は李園の放った刺客に殺害されてしまうのでした。
古代中国をもっと詳しく知るためのおすすめ書籍
『現代語訳 史記』司馬遷・著、大木康・翻訳(ちくま新書)

歴史書の大古典にして、生き生きとした人間の在り方を描く文学書でもある司馬遷の『史記』を、「キャリア」をテーマにして選び出し現代語訳。帝王、英雄から、戦略家、道化、暗殺者まで、権力への距離は異なっても、それぞれの個性を発揮し、自らの力で歴史に名を残した人物たちの魅力は、現代でも色あせることはない。適切なガイドと本物の感触を伝える訳文で『史記』の世界を案内する。
『戦争の中国古代史』佐藤信弥(講談社現代新書)
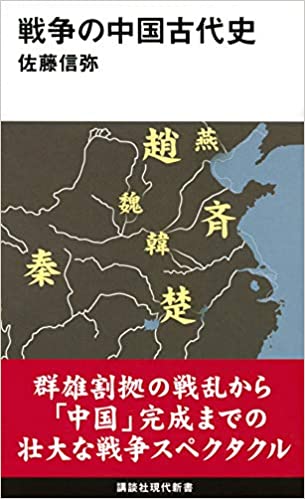
群雄割拠! 殷・周・春秋戦国時代に繰り広げられた古代中国の戦争を軸に、「中華帝国」誕生の前史を明らかにする画期的入門書。
『古代中国の24時間-秦漢時代の衣食住から性愛まで』柿沼陽平(中公新書)

始皇帝、項羽と劉邦、武帝ら英雄が活躍した中国の秦漢時代。今から二千年前の人々は毎日朝から晩まで、どんな日常生活を送っていたのだろう? 気鋭の中国史家が史料を読み込み、考古学も参照しながら、服装、食事から宴会、セックス、子育ての様子までその実像を丸裸に。口臭にうるさく、女性たちはイケメンに熱狂し、酒に溺れ、貪欲に性を愉しみ……驚きに満ちながら、現代の我々とも通じる古代人の姿を知れば、歴史がますます愉しくなる。



















