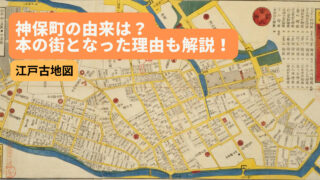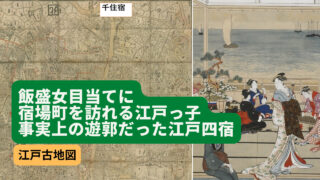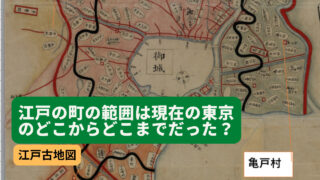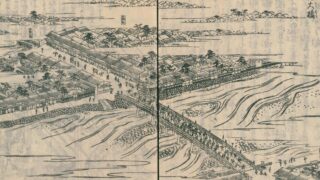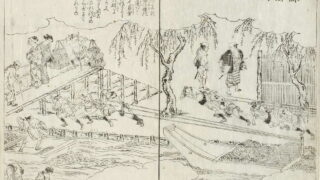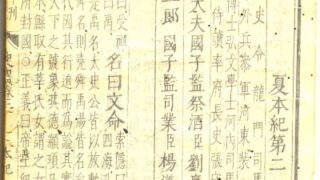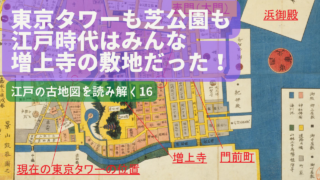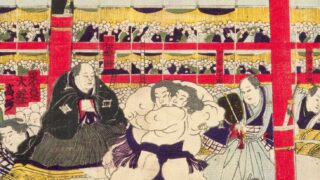江戸時代にはじまった七福神巡り
しばしば宝船に乗った姿で描かれる七福神は、福をもたらす存在として多くの信仰を集めています。しかしその歴史は意外と浅く、七福神信仰が生まれたのは室町時代末期のことだといわれます。
当時、神社は庶民の財宝や官位などを得たいという欲求に応える形で福神の宣伝につとめました。そのなかで恵比寿・寿老人・福禄寿・布袋・毘沙門天・弁財天・大黒天の福神がまとめて「七福神」と呼ばれるようになり、七福神信仰が盛んになったと伝わります。
江戸時代には正月2日の夜、宝船に乗った七福神の絵を枕の下に敷いて寝ると幸運が訪れると信じられました。また、元旦から七草までの期間に七福神を祀った寺社を巡り、1年の無事や幸福などを願う「七福神巡り」がはじまったのもこの頃のことです。
現在も「江戸山手最初七福神」や「日本橋七福神」、京都の「都七福神」など、さまざまな七福神巡りが親しまれています。
七福神はどんな神様?
七福神のなかで、日本の神なのは恵比寿だけです。大国主神の御子神・事代主神ともいわれます。漁業や農業、商売繁盛の神として古くから信仰を集めてきました。大国主神が大黒天と習合したことから、恵比寿・大黒天としてともに祀られることもあります。
大黒天と弁財天、毘沙門天は、もともとはインドの神でした。大黒天はインドでは暗黒神マハーカーラーでしたが、仏教に取り入れられて台所を守る神とされました。日本でも当初は寺院の台所に祀られましたが、やがて音が通じることから大国主神と習合し、恵比寿とともに福の神として崇められるようになったのです。
一方、弁才天は川の女神サラスヴァティが原型で、水や音楽、財宝を司るとされました。毘沙門天のもと軍神バイシュラバナ。財や富を司る神です。
福禄寿と寿老人、布袋はそれぞれ中国の神です。布袋は9~10世紀に活躍した禅僧・契此が神格化されたもの。常に袋を持っていたことから布袋と呼ばれるようになりました。円満の神として信仰を集めます。
福禄寿と寿老人は南極星を神格化したものです。どちらも延命・長寿の神です。福禄寿と寿老人をまとめて、代わりに吉祥天を七福神に入れる場合もあります。
神社についてさらに詳しく知りたい方におすすめの書籍
『神社の解剖図鑑』米澤貴紀(エクスナレッジ)
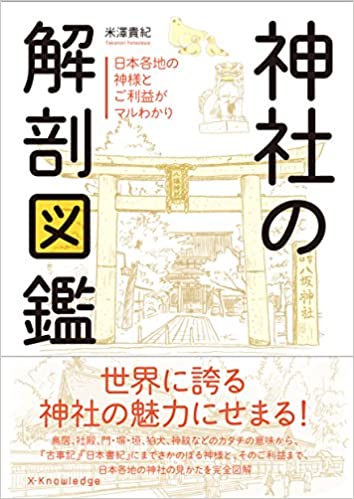
鳥居、社殿、門・塀・垣、狛犬、神紋などのカタチの意味から、『古事記』『日本書紀』にまでさかのぼる神様と、そのご利益まで、日本各地の神社の見かたを完全図解。
『神社のどうぶつ図鑑』茂木貞純監修(二見書房)
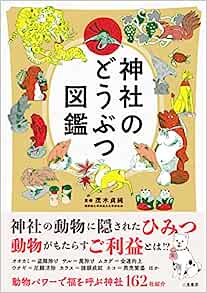
神社を訪れると、狛犬やキツネなど様々な動物の像を見ることができます。「どうして動物がいるのか?」不思議に感じている人も多いことでしょう。これらの動物は神に仕えるものと考えられ、神使あるいは眷属(けんぞく)といわれています。姿を現さない神々の代わりに、ゆかりのある動物が神の意志を人々に伝えると考えられてきたのでした。
本書は神使として祀られている54種類の動物の由来やご利益、動物を大切に崇めている日本全国約162の神社を紹介しています。
『神社の解剖図鑑2』平藤喜久子監修(エクスナレッジ)
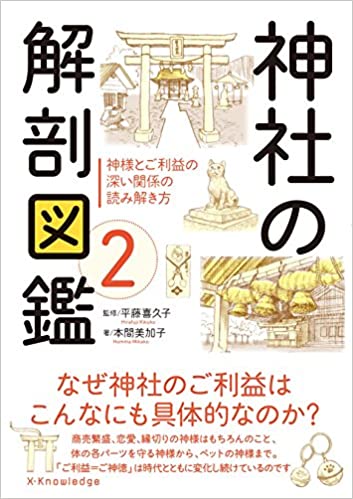
なぜ神社のご利益はこんなにも具体的なのか? がマルわかり。本書は神社と神様とご利益の関係をイラストを使って徹底解剖!神社をもっと身近に感じ、祀られている神様のことが深く理解できるようになります。