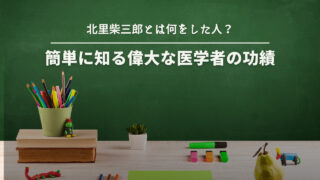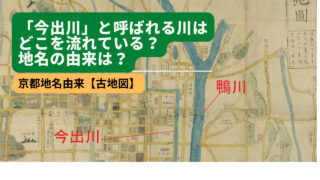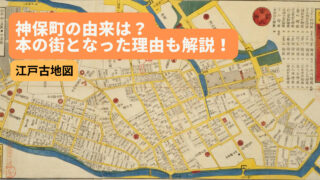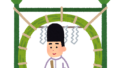浮世絵DATA

【タイトル】『東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景』
【作者】歌川広重初代(1797~1858年)
【制作年】天保4~5年(1833~34)頃
浮世絵解説
東海道の起点である日本橋の朝の風景を切り取った作品。
早朝、東の空から太陽がのぼりはじめると、明6つ(午前6時頃)を知らせる時の鐘の音が江戸市中に鳴り響き、それを合図として各町の木戸が開け放たれた。手前に見えるのが、その木戸である。
橋の中央を渡ってくるのは、参勤交代の大名行列。参勤交代には、とてつもなく多額の費用がかかった。少しでも旅費を減らすため、各藩はなるべく朝早くに出立するのが常だった。先頭の二人が担いでいるのは、大名の着替えや日用品などが入った挟箱。行列の中で高く掲げられているものは毛槍という。2本掲げているので、この行列が3万石以上の大名のものであることがわかる。
一方、橋の手前には、棒手振と呼ばれる行商人が描かれる。当時、日本橋には朝の商いだけで1000両(約1億円)もの金が落ちるといわれた魚河岸があった。漁師から卸された魚は棒手振を通じて江戸の町へと行き渡ったのである。
棒手振の近くに描かれている立て看板は、「高札」と呼ばれる。庶民に法令を知らしめるために設置されたもので、橋の近くなど人が集まる場所に置かれるのが常だった。
橋の欄干につけられた装飾は、擬宝珠という。橋の格を示すものであり、江戸市中では、日本橋のほか京橋、新橋と3つの橋のみに配された。
江戸時代の暮らしをさらに詳しく知りたい方におすすめの書籍
『一日江戸人』杉浦日向子(新潮文庫)
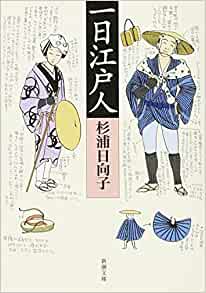
現代の江戸人・杉浦日向子による、実用的かつ、まことに奥の深い江戸案内書。
江戸美人の基準、三大モテ男の職業、衣食住など、江戸の人々の暮らしや趣味趣向がこれ一冊でわかる。試しに「一日江戸人」になってみようというヒナコ流江戸指南。
『現代語訳 江戸府内絵本風俗往来』菊池貴一郎(角川ソフィア文庫)
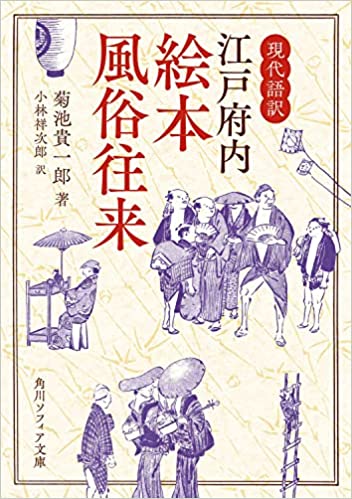
四季の行事から、日常の風景まで。江戸の風情を283点の絵と文で愉しむ。江戸の町の季節の移ろいや、武家・町人の行事・習俗・遊びのさまざまを、イラストとともに回顧する。江戸を知るための基本書、初の現代語訳。図版283点のすべてを収録。
『浮世絵の解剖図鑑』牧野健太郎(エクスナレッジ)
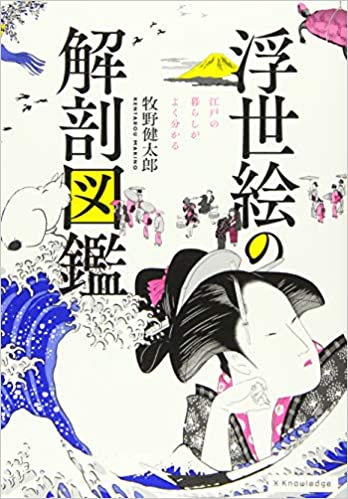
傑作と呼ばれる葛飾北斎の『富嶽三十六景』から歌川広重の『東海道五十三次』、通好みの1枚まで名作浮世絵から、江戸の街と暮らし読み解く。浮世絵の中に隠された謎やお江戸の洒落、庶民の知恵、江戸っ子たちが面白がっていた遊び心を読み解き、浮世絵の本当の楽しみ方を紹介。浮世絵やアート好きだけでなく、江戸や歴史に興味がある方にもおすすめの1冊。