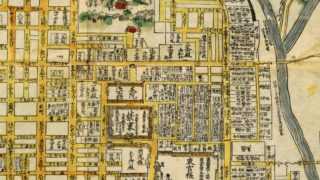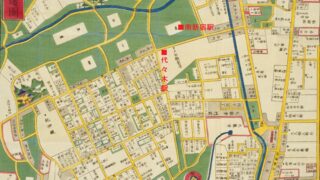臥薪嘗胆がしんしょうたんの意味
仇を取るために苦労すること。将来の成功のために苦労すること。
臥薪嘗胆の出典
『十八史略』
臥薪嘗胆の由来
呉王・夫差は父を越に殺された復讐のため、常に薪の上に寝て、家臣が自身の部屋に入るときは「越人が汝の父を殺したのを忘れたのか」と叫ばせるようにした。そしてついには越を討ち取り、父の仇を取ることに成功した。
このとき、越王・勾践は夫差に絶世の美女である妻を献上し、助命を請うた。その後、勾践はあらゆる恥辱に耐え忍び、やがて越への帰国を許された。その後、勾践は生の胆を吊り下げ、その苦味をかみしめながら復讐の刃をといでいった。
以上の故事にもとづき、夫差の「臥薪」、勾践の「嘗胆」が組み合わせられ、仇を取るために苦労するたとえとして「臥薪嘗胆」が用いられるようになった。
故事成語をもっと知りたい方におすすめの書籍
『中国史で読み解く故事成語』阿部幸信(山川出版社)
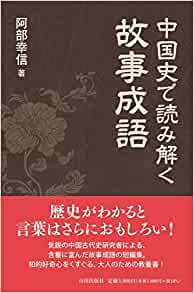
中国史のエピソードを添えて、100の故事成語を解説した短編集。言葉本来の意味やその変遷なども踏まえつつ、現代へのメッセージも光る。一般教養としてだけでなく、中国史ファンや漢文の愛好家にも楽しんでいただける一冊。
『マンガで分かることわざ・故事成語 上』ゆうきゆう(少年画報社)
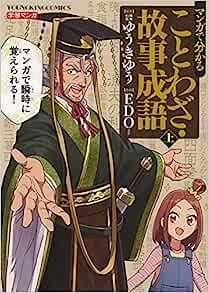
ことわざや故事成語が苦手なイチくんとレイちゃんがことわざ博士に出会い、タイムマシンを使って当時の故事成語を体感してお勉強!知っているようで説明しようとすると難しいことわざや故事成語をゆうきゆうがわかりやすくお届けします!笑って勉強にもなる子供にも読ませたい1冊!
『こども故事成語: 怒髪天を衝く』齋藤孝(草思社)
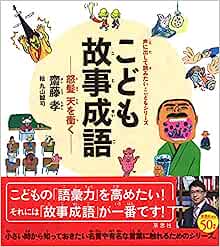
子どもの語彙力を高めるには、「故事成語」がいちばん!「五十歩百歩」「塞翁が馬」「君子は豹変す」「呉越同舟」……などの少し難しい漢字が使われる慣用句は、中国の故事・昔話などから出来たもので「故事成語」と呼ばれる。言葉の背景にあるエピソードが面白いので子どもにも覚えやすい。言葉の背景となっている故事を楽しい絵と齋藤先生による丁寧な解説で理解しやすいようにした、子どもの語彙力を高め、国語力をつけるための最適の絵入り解説書。